パスの質にこだわれない理由

池上正さんの「蹴る・運ぶ・繋がる」を体系的に学ぶジュニアサッカートレーニングという本を読み返していました。
そして、
「1対1だけでは、パスをするキックの技術やコントロールする技術は身に付きません」
「蹴る・運ぶ・繋がる」を体系的に学ぶ ジュニアサッカートレーニング
という一節に目が留まりました。
まさにその通りだと頷きました。
そもそも1対1にはパスというものが無いので、パス技術が身に付くわけがありません。
Contents
パスを蹴ればいいというものではない
そしてパスというものはパスを蹴ればいいというものではありません。
味方が取りやすいボールであり、敵がとりにくいボールである必要があります。
パスの質にこだわる必要があります。
それは「ボールが奪われずにボールを繋げる」ためです。
先日、ジュニアクラブユース選手権の県予選を見に行ってきました。
そこで見えたのが、トラップをミスしてボールを奪われるという数々の場面です。
そしてこのミスはトラップ技術が原因というよりもパスの質によって起こっていると感じたわけです。
そのパスには「奪われていはいけない!繋げる!」という意図がありませんでした。
パスの質にこだわりがないのです。
ゆえにボールが弾んで、受け手にはとりずらいボールになっていました。
変わらない練習内容
なぜこういったことが起こるのか?
それは「奪われていはいけない!繋げる!」の意識が薄いということにつきるのですが、上記の一節を見るとジュニア時代に1対1の練習を主に行ってきたからではないか?と考えてしまうわけです。
実際、息子が通っていた少年団がそのような指導でした。「1対1で勝たなければいけない!」といった古い考えです。
言ってみれば「タイマン勝負」を愛する古い考えです。
しかしサッカーに必要な考えは、
✅相手が1人なら2人。
✅相手が2人なら3人
というように「人数を増やせば勝てる!」というものです。
1対1ではなく2対1のトレーニングが主であったらどうでしょう?
「蹴る・運ぶ・繋がる」を体系的に学ぶジュニアサッカートレーニングに書かれているように、1対1で得らえるドリブル技術以外に「パスをするためのキック技術」も習得できます。
遅いパスでは敵に奪われます。速いパスでないといけません。しかし「速くなければ!」といって取りにくいボールでは繋がりません。
いかに速いパスで繋がるボールを蹴らなければいけないことを考えるようになります。
また敵の状況によってもパスの質も変わるでしょう。味方の位置や体の向きによっても変える必要があります。
要するに、パスの技術がただ単に高まるのではなく、繋げるための思考力も高まるわけです。
1対1では繋げる思考は築かれない
サッカーは
✅ボールを奪い
✅ボールを奪われずに
✅ボールを繋げ
✅ゴールを奪う
スポーツです。
1対1だけでは繋げる思考は高まりません。繋げる思考がなければゴールを奪うことはできません。
ゴールを奪えなければ勝つことはできないわけです。
サッカーに置いて一番大事な練習に特化するべきだと考えます。

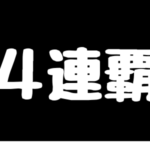





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません